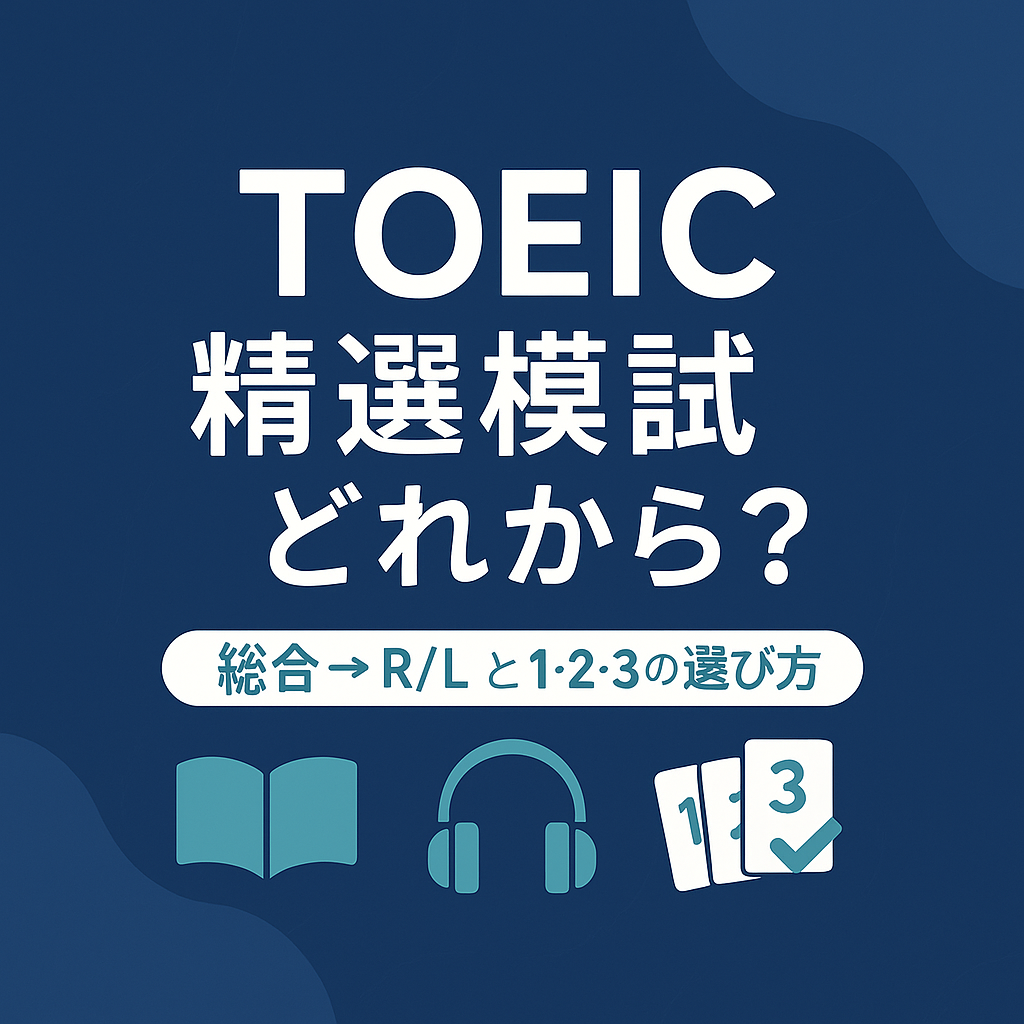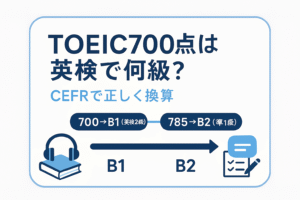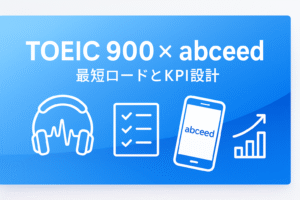「リーディングから?リスニングから?“1・2・3”はどれ?」――精選模試は名著ゆえに選択肢が多く、最初の一冊で迷いがち。本記事はスコア帯/弱点/学習時間の3条件から、最短ルートを提示します。さらに総合(R+L)の出番、1/2/3の違い、復習の回し方まで、買ってから迷わない導線を具体化しました。
本記事での「どれから」の意味
- A|カテゴリ順:総合(R+L)→ R または L、どちらから始めるか
- B|巻順:精選模試の1・2・3のどれから買うか
まず結論を示し、その後に各分岐の理由と手順を解説します。
1. 結論:あなたはどれから?目的別フローチャート
1-1. まず「総合」で現在地診断すべき人
直近で本番形式の通しを受けていない/弱点の自覚が曖昧/スコア停滞の原因が不明――このどれかに当てはまるなら総合(R+L)から入るのが最短です。総合は200問×2回=計400問。時間通りに解いて即採点し、誤答を「語彙」「文法」「推論」「設問把握」「時間切れ」などにラベル分け。補助素材(設問一覧・要点リスト・音声)を活用して弱点にピンポイントで“処方”を当てます。1回分を「本番通し→採点→原因特定→補強→再演習」まで回すと、次に R または L どちらを優先すべきかが点(数値)と手触り(体感)の両面で明確化。以降の投入時間の歩留まりが跳ね上がります。
1-2. R から始める人/L から始める人
R から:設問読み落とし・根拠の局在化の遅さ・時間切れが主訴。精選模試Rは1冊で5模試=計500問の“読解スタミナ”が貯まるため、Part5〜7の地力が底上げされます。
L から:文面は読めるのに聞き取りと設問先読みが崩れるタイプ。精選模試Lも5模試=計500問の“聴解ループ”を組めます。
迷う場合は「総合 → 弱点側(R または L)」という順でOK。特化と総合の役割分担を意識して、最短でボトルネックを潰しましょう。
2. 精選模試の種類・仕様と難易度の事実
2-1. R/L は各500問、総合は400問
仕様の要点はシンプルです。リーディング/リスニングの各巻=100問×5回=計500問。総合=200問×2回=計400問。分冊(R/L)は“量の特化”、総合は“実戦再現+復習導線(要点リスト/音声等)”という立ち位置。分冊は各問の正答率の目安が参照でき、難問で落としたのか自分の穴で落としたのかを切り分けやすい設計です。
2-2. なぜ“本番に近い”と言われるか
精選模試は本番に非常に近い〜やや高めと語られることが多い教材です。練習段階で“やや高地”に身を置くことで、本番での想定外(難化や問われ方の揺れ)を想定内にできます。一方の公式問題集は“出題作法の確認”に最適。精選模試=地力+本番対応力、公式=出題作法の参照と捉えると併用戦略が取りやすくなります。
※巻・版により付属/提供形態(音声・正答率表示など)が異なるため、購入前に商品ページで最新情報の確認を推奨します。
3. 「1・2・3」どれから?違いと選び方
3-0. 「1・2・3」はどれから買う?(結論)
結論:在庫/価格などの入手性 → 音声運用(DL/アプリ) → 継続計画の順で選べばOKです。公式に巻ごとの難易度差は明示されていないため、順番よりも回す量と復習設計が成果を左右します。
- 入手性:すぐ始められる巻を優先(最新版/在庫安定)
- 音声運用:自分が続けやすい形(MP3/アプリ/学習アプリ連携)
- 継続計画:まず1巻を20日サイクルで回し、定着したら2 → 3へ
3-1. 難易度は概ね同等:最新版からでOK
「1・2・3のどれが簡単/難しい?」は気にしすぎなくて大丈夫。実用上はどれも難易度はおおむね同等で、在庫や価格、手に入れやすさで決めてOKです。複数巻を回すなら、入手性 → 価格 → 音声の扱いやすさで優先度を付けるのが現実的。R/L×3巻=計1,500問という“同難度×量”の努力が、結果的に最短になります。
3-2. 音声・デジタル活用(アプリ連携)
解答・採点・音声再生・弱点分析をまとめて回せる学習アプリと併用すると回転速度が段違いになります。紙派でも、音声ダウンロードや再生アプリを常時使える状態にしておくと“耳の稼働時間”が増えて定着が加速。おすすめは「紙+音声アプリ」、または「アプリ一元管理」のどちらかに統一して、迷いなく回せる環境を作ることです。
4. スコア帯別:最短ルートの学習手順
4-1. 〜600:読解体力の底上げ(R → 総合)
この帯のボトルネックは「速度 × 精度 × 根拠の可視化」。推奨は「R1 →(誤答分析)→ R2 → 総合1回 → R3 → 総合1回」。復習は根拠マーク/文構造分解/パラフレーズ収集/“根拠の日本語一行化”の4点セットで“再現性”を作る。時間が取れない人は20日サイクル(Day1-10=解く&直す、Day11-20=寝かし&再演習)で、意味の既視感を仕込むと伸びが安定します。
4-2. 600〜800:弱点特化 → 総合 → 本番想定
この帯は偏りの是正が最短。フローは「総合1回 → 弱点側(R または L)1〜2巻 → 総合1回 → 反対側1巻 → 直前は総合を時短通し」。正答率データを手がかりに“難問で落とした”のか“自分の穴で落とした”のかを峻別し、穴に投資。直前2〜3週間は総合の通し×2〜3で、本番の呼吸と配分を合わせます。
4-3. 800〜:総合 × 誤答原因特定 → 微修正
800超は1点単価が高い帯。総合で通し→誤答を「先読み破綻/ディストラクタ選別ミス/情報統合の遅延」にラベリング。L はキー語の音変化・弱形の拾い上げ、R は設問根拠の局在化を徹底。Part2・6・シングルなど“確実に拾える設問”の取りこぼしを最優先で潰すと、短期でもスコアが動きます。
5. 復習が命:採点→原因→類題の回し方
5-1. 正答率データの読み取りと優先順位
復習の黄金律は「高正答率の取りこぼし > 低正答率の難問」。高正答率で落とした問題は“みんな解けるのに自分だけ落とした穴”で、最も費用対効果が高い領域。逆に低正答率は、戦略(スキップ・見切り)で回収可。誤答ノートは「設問タイプ/誤答タイプ(語彙・文法・推論・先読み破綻など)/修正アクション」を1行で記録すれば十分機能します。
5-2. 20日サイクルで“理解→定着”
20日×1周のモデル例:
・Day1-10:1日1/2〜1模試を解く→直すに集中(音声は移動中に常時再生)
・Day11-20:誤答を寝かせたのち再演習。パラフレーズや根拠の再抽出が即答に変わっているかを確認
この“寝かし”を挟むだけで長期記憶への橋渡しが進み、「分かったつもり」を防げます。
6. よくある疑問Q&A
Q1. 公式問題集と精選模試、どっち先?
A. 設問作法の参照には公式、地力+本番対応力強化には精選。迷うなら精選の総合 → 分冊 → 公式で作法確認が回しやすい順序。
Q2. 何周すべき?
A. 通しは各回最低2周(本番通し → 補強 → 再演習)。分冊は弱点パートを3〜4周の分解練習まで回すと効果が安定。
Q3. 時間配分の目安は?
A. R はPart5:10〜12分/Part6:8〜10分/Part7:55〜60分を基準に、自分の得点源へ秒配分を再配当。L は先読み > 聞き取り > 即断の順で体幹づくりを。
7. 失敗例と回避策
解きっぱなし:採点で終わらない。原因ラベリング → 補強 → 再演習までを1セット化。
音声軽視:L は英文だけ見ても伸びにくい。音 → 文字 → 意味の往復で耳の稼働時間を増やす。
速さ優先:速度は根拠の即時化の副産物。先に正確さ(根拠局在化)を固める。
8. まとめ
迷ったら原則は「総合 → 弱点特化(R または L)」。総合は200問×2回の実戦で現在地を測り、分冊は同難度×量で地力を底上げします。「1・2・3」の難度差は実用上ほぼ同等なので、入手性と価格で決めてOK。復習では高正答率の取りこぼしを最優先に潰し、20日サイクルで“理解→定着”を回しましょう。練習は本番よりほんの少しキツめ――それが当日の不確実性を味方に変える最短ルートです。最初の一冊、そして最初の1セットを今日から始めてください。
次アクション
- 総合を1回通し(時間厳守)→ 誤答ラベリング
- 弱点側の分冊を選ぶ(入手性・音声・連携)
- 20日サイクルをスケジュールに落とし込む

かっしー
TOEIC770点 → 900点を目指して勉強中✍️
2025年10月に英検準1級を受験予定です。
独学で積み上げた学習法や教材レビューを発信中。
「効率よく成果を出す英語学習」をテーマに、ブログとXで情報をシェアしています。