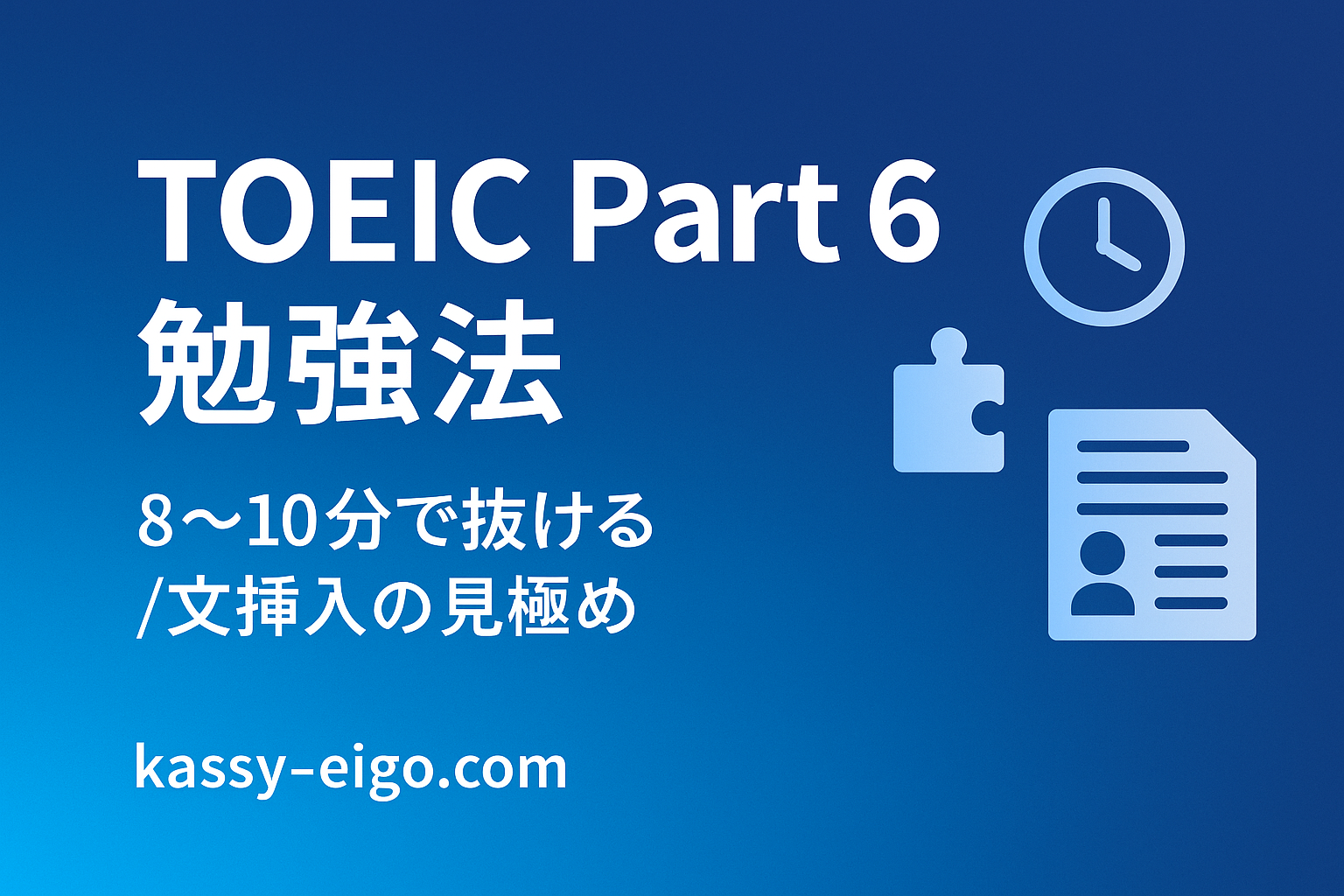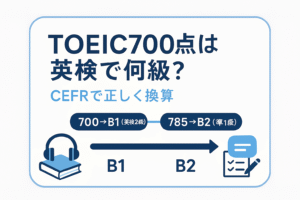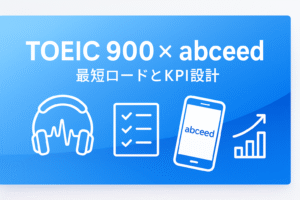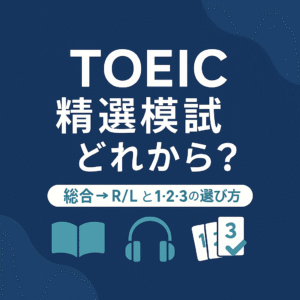Part6に時間を吸われてPart7が塗り絵——よくある悩みです。原因は「文挿入の見極め」と「時間配分の基準」が曖昧なこと。本記事では、Part6を8〜10分で抜けるための解き方(固定手順)と、設問タイプ別のコツ、2週間の練習メニュー、復習テンプレまでを一式で示します。今日から迷いなく、スコアに直結する勉強だけに集中しましょう。
1. Part6の全体像と得点設計
1-1. 出題構成と問われる力(16問/4パッセージ/文挿入)
Part6は約100語前後の短い文書が4つ出題され、各文書に4つの空所=計16問で構成。空所は大きく「文法・語彙(品詞・時制・コロケーションなど)」と「文挿入(1文そのものを挿す)」の2系統です。文挿入は段落の論理や指示語(this/that/it/they、冠詞の定・不定)、談話標識(however, therefore など)と照応関係を捉えないと正解しづらいのが特徴。まずは「文書タイプ(email/notice/articleなど)」を掴み、空所タイプを識別、根拠一致を確認する流れを固定化しましょう。
1-2. なぜPart6は“8〜10分”が基準なのか(Part7への配分)
リーディング全体は75分100問。Part6は理論上12分使えますが、Part7(54問)が最も時間を要します。高得点者はPart6を8〜10分で切り上げ、Part7に55分前後を残すのが共通戦略。「1問30〜40秒」「1パッセージ2分」を感覚で持てるよう、普段の演習から本番速度で回すことが重要です。
2. 設問タイプの見取り図
2-1. 文法・語彙:品詞/時制/コロケーション
- 品詞:冠詞+__+名=形容詞/前置詞+__=名(動名詞含む)など、機能語で絞る。
- 時制・態:時表現(yesterday/currently/by the end of…)や be+過去分詞 との整合を最優先。
- コロケーション:meet a deadline, place an order, take place など定番の相性で秒速判断。
- 迷えば文の骨格(S/V/O/C)を再構成し、余計な新情報が突然登場していないかを確認。
2-2. 文挿入:位置の役割と判断材料(冒頭/中段/末尾)
- 冒頭:テーマ・目的などの導入が入りやすい。
- 中段:前後の橋渡し(転換・具体化・因果・対比)。指示語・定冠詞・同一名詞の反復に注目。
- 末尾:まとめ・依頼・次アクションが配置されやすい。
- 選択肢に初出概念があるのに本文側に導入がなければ不適。this/theseがあるなら直前の複数名詞列挙を探す。
3. 時間配分と順番戦略
3-1. 8〜10分の配分サンプル(1パッセージ2分目安)
- (a)文書タイプを一瞬で特定(1〜2秒)→(b)段落主旨をなぞる(15〜20秒)
- (c)語彙・文法型を先に秒速処理(各10秒)→(d)文挿入は最後に回す(30〜40秒)
- 2分を超えそうなら△マーキングして次のパッセージへ。最後に△だけ回収。
3-2. “飛ばす”基準(スコア帯別の判断)
- 600〜700点目標:語彙・文法で確実に拾う。文挿入は最後回収でもOK。
- 800+目標:文挿入も基本回収。ただし迷いは即△→終盤で再判断。
- 全体最適=Part7に55分前後を残すこと。Part6で抱えない。
4. 解答プロセスの固定化
4-1. 手順:先読み→全体像→タイプ別処理→検算
- 先読み:文書タイプ(email/notice/article)と目的(案内/依頼/謝意/告知)を予測。
- 全体像:段落の役割(1段=目的、2段=詳細、3段=依頼…)を把握。
- タイプ別処理:語彙・文法は品詞/時制/コロケで秒速判断。文挿入は位置の役割×照応×談話標識で即断。
- 検算:入れた語・文で流れが滑らかか。突然の新情報が紛れていないかをチェック。
4-2. 瞬時にタイプ判定するチェックリスト
- 品詞?(冠詞/前置詞/修飾の形)
- 時制・態?(時表現との一致)
- コロケ?(業務系頻出の相性語)
- 談話標識?(however/therefore/for example)
- 指示語の照応?(this/that/these/it の参照先)
- 名詞の初出/再登場は自然?(the/代名詞の使い分け)
5. 2週間の学習ロードマップ
5-1. Day1–7:基礎固め(1日30分の最小セット)
平日は「Part6 1セット(2パッセージ)×本番速度」→「復習テンプレ」でOK。文法・語彙は解いた問題の中だけを深掘りし、辞書参照は5分以内。週末に4セットまとめて回し、8〜10分で完走する感覚を作る。語彙は本文から拾ってノート化→翌日に文で音読してフレーズ化。
5-2. Day8–14:本番速度→再テスト中心で定着
- Day8–10:4セット通し×2周(時間計測)。
- Day11–13:△マークリストのみ再テスト。
- Day14:模試1回。KPIはスコアよりPart6終了時点の残時間(8〜10分で切れたか)。
6. 復習と定着(テスト効果を使う)
復習は“読む”より再テストが効きます。①初回は時間計測して解く→②誤答の原因1行メモ(指示語照合ミス/品詞誤判定など)→③翌日に同じ問題だけ再テスト→④1週間後にもう一度。原因タグ(例:anaphora/tense/collocation)を積み上げ、タグの減少を上達の指標にしましょう。
7. よくあるミスと修正法
7-1. 文挿入で“語彙の近さ”に釣られる/指示語の照合抜け
- 似た語があっても、談話上の役割がズレていれば不正解。前後2文で主語・指示語・談話標識を検算。
- that/this/it/they の参照先が曖昧なら保留(△)→最後に回収。
8. 教材の選び方と使い分け
まず公式サンプルや公式問題集でフォーマット把握→精選模試などで分量を確保→アプリ(タイマー・分析)で8〜10分の感覚を毎回可視化。周回数ではなく、誤答原因の種類が減っているかで管理しましょう。
9. スコア帯別アプローチ(600/700/800+)
- 600目標:語彙・文法で取り切る。文挿入は最後回収でもOK。
- 700目標:文挿入の「位置×照応×談話標識」で回収率6→8割へ。
- 800+目標:迷い即△→終盤30秒で再判断。Part7の時間死守を最優先。
まとめ
Part6は「型を決めて速く正確に処理する」パートです。中核は(1)語彙・文法を秒速処理する基礎力、(2)文挿入を位置の役割×照応×談話標識で即断する読解力、(3)本番速度の計測と再テスト中心の復習設計。全16問を8〜10分で抜けてPart7に55分前後を残す——この時間戦略がスコアの土台になります。記事のロードマップを2週間回せば、Part6終了時の残時間が安定し、Part7の正答数が伸びるはず。迷いは即△、最後に回収。“抱えない”ことが最速の正解です。

かっしー
TOEIC770点 → 900点を目指して勉強中✍️
2025年10月に英検準1級を受験予定です。
独学で積み上げた学習法や教材レビューを発信中。
「効率よく成果を出す英語学習」をテーマに、ブログとXで情報をシェアしています。