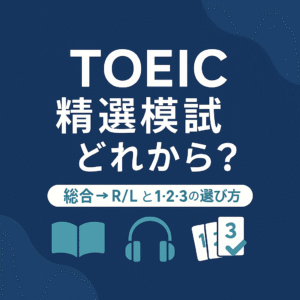Part4の長めのアナウンス/広告/案内が聞き切れず、3問セットで崩れる——そんな悩みを、先読みの“型”、タイプ別の聞き方、1日90分の演習ループで解決します。時間配分・図表・意図問題まで、起きやすい順に対処法をまとめました。
1. Part4の全体像と前提
1-1. 出題形式・問題数・本文仕様
Part4は「短い説明・案内・広告などの独話(talks)を聞いて3問答える」セクション。合計30問(10トーク×各3問)。問題冊子に印刷されるのは“質問と選択肢のみ”で、本文スクリプトは掲載されません。1トークはおよそ30〜40秒、設問読み上げ間隔は短く、1問で粘ると次の2問も落としやすい構造です。後半セットでは表・カレンダー・座席などの図表参照型が出ることがあり、視覚情報の処理も得点源になります。
1-2. 配点イメージと目標正答数
- 600点狙い:各セット2/3正解=計20/30を下限
- 700点前後:23〜25/30を安定ライン
- 800点以上:27/30以上(落としてよいのは2〜3問)
鍵はセット思考。1トークで3連落ちを避けるため、主旨+具体を確保し、推測は状況で切る優先順位を準備。図表は対策コスパが高いので事前に固めます。
2. まず固める基礎技術
2-1. 「7秒先読み」の型づくり
先読みは最大のレバレッジ。手順は「Q1〜Q3の疑問詞+名詞をなぞる→選択肢は“差がつく語”だけ拾う」。when/where/why/what+名詞(event, refund, delivery など)を確認し、選択肢は日付・時刻・場所・担当・金額・行き先など“軸”に絞る。最初は10秒かけてもOK。慣れたら約7秒以内で完了を目標に。問われる軸を先に頭へ置くことで、本文開始直後に「話者・目的・場面」の三点認識が固まり、歩留まりが跳ね上がります。
2-2. キーワードの見つけ方と“捨て語”
先読みで拾うのは正誤を分ける差分語。固有名詞(Mr. Chen / Gate 12 / Downtown)、時間・日付(by Friday / at noon)、数量・金額(two boxes / 20 percent off)、手配語(confirm / reschedule / refund)など。背景語(nice, important など)は捨て語として意識から外す。本文ではパラフレーズ(discount⇔money off、repair⇔fix…)が定番。言い換え網をノート化し、先読みメモに“=表記”で並べると命中率が伸びます。
3. 出題タイプ別の聞き方
3-1. アナウンス/広告
“誰に→何を→いつどこで→なぜ→どうしてほしいか”の順で流れやすい。冒頭10秒で話者(店員/主催者/運営)と目的(告知/案内/謝罪/依頼)を確定。中盤の具体(日時・場所・価格・条件・連絡先)に耳を置く。広告は「メリット→条件→CTA(call us / visit our website)」の定番。答えは条件に埋まることが多いので、ポジティブ表現に惑わされず条件文を必ず拾う。
3-2. 留守電/依頼・指示
“要件→理由→依頼/指示→締め(折返しや期限)”の型。先読みで「誰が誰に」「何をしてほしいか」を明確にし、本文では依頼動詞(ask, remind, need, arrange)と期限語(by, before, this afternoon)を待ち受ける。人物関係と行動語が一致する選択肢を選ぶ。
3-3. 案内・ツアー/プレゼン
“場所→手順→注意→例外→CTA”の順に出やすい。案内は否定・例外の一言(except, unless, instead)が鍵。プレゼンは構成マーカー(first, next, finally)と対比(however, although)を根拠にする。
3-4. 図表問題(表・カレンダー・座席)
図表は見る順を固定。先読み時に図の軸を1秒把握(縦=担当/横=時刻など)→設問で問われる要素に印→本文では「図のどこが更新されたか」だけ聞く。数字・曜日・地名はパラフレーズが起きにくい=点取り所。10〜20題を束で回し、“見る→聞く→指差す”を身体化。
4. よく落とす設問タイプ
4-1. 意図・目的を問う問題
“なぜ話しているか/何を意図しているか”。根拠は接続語とCTA(because/so/therefore/however…+visit, call, register など)。先読みで why / purpose / intend をマーキング。気持ちではなく機能で読む。
4-2. 推測(次の行動/理由)
本文の明示されない関係を補完。根拠は本文内にあり、転換・対比・因果(due to, in order to, although, instead)が信号。A/Bの役割(顧客⇔店員、主催⇔参加者)を即確定し、立場に合う行動を選ぶ。
4-3. 具体情報(数字・固有名詞)
“数字・時刻・地名・人名・金額”は回収すれば点に直結。弱点はメモの整形ミスになりがち。メモは軸ごとに列で書く(例:時刻|場所|担当)。“近いが違う値”は典型的な罠。
5. 1日90分:高速学習ループ
5-1. 公式問題集の回し方(1回転)
- 通し演習(タイマー厳守)
- 答え合わせ(正解の根拠英文を必ず確認)
- スクリプト精読(パラフレーズ網を抽出)
- ディクテーション(抜けた文を2回まで)
- シャドーイング(等速→1.1倍)
これを1セット=9問単位で回すのが最短。他選択肢が×の理由(未言及/矛盾)まで言語化。先読みメモ→本文→設問の照合ログで“的中語”を増やす。
5-2. ディクテーション&サイトトランス
聞こえなかった箇所だけ部分ディクテ(2回まで)→埋まらなければ答えを見て原因分類(音変化/弱形/語彙不足/集中切れ)。その後、英文語順のまま意味を追うサイトトランスレーションで処理速度を上げ、最後にシャドーイングで音の連結・脱落を身体化。1セット30〜40分、1日90分で2〜3セット。
5-3. シャドーイング&オーバーラッピング
「意味シャドー → メトロノーム(音合わせ) → オーバーラップ(スクリプト見ながら完全一致)」の順に強度を上げる。録音して数字・固有名詞・機能語のズレを自己採点。週3〜5回、各10分でOK。
6. スコア帯別の戦略
6-1. 〜600点:型と語彙を同時進行
先読みの手順を音読で固定しつつ、日付・時刻・場所・金額・依頼動詞の頻出語を最優先で暗記。図表はカレンダーから慣らし、1日1セット(9問)を正確さ優先で回す。
6-2. 700点前後:タイプ別処理の高速化
“1セット2/3確保、難問は切る”。タイプ別テンプレを明文化し、先読み→本文→設問の手と耳の動線を短縮。図表は毎日10題の束練で自動化。誤答は「先読み/本文/設問」のどこで落としたかをチェックし、同種ミスを翌日で潰す。
6-3. 800点〜:意図問題・図表の満点化
捨て問を作らず取り切る設計へ。意図・推測は接続語とCTAを根拠に処理。図表は“更新点”を素早く検出。先読みは7秒以内・精度9割を目標に、音源は公式準拠で回数より質を追う。
7. 当日のオペレーション
7-1. 時間配分と切り捨て基準
音声のお尻を追わない。2秒迷ったら即マーク→次へ。先読み7〜10秒を死守し、設問は「主旨→具体→推測」の順に優先。図表セットは開始前に図をざっと舐め、本文で更新点だけ聞く。損切りで全体を守る。
7-2. マーク運用と復帰のコツ
迷ったら“消去法で最有力”に賭けるルールを事前決定(例:C/D優先)。塗りつぶしを統一し、復帰時の視線移動を最短に。焦りを感じたら深呼吸→先読みの手順に戻る。
7-3. 事故った時のリカバリー
1セット全滅の気配なら、いったん推測問題を後回しにし、“取りやすい具体”を確保。直後のセットで図表が来る可能性もある。模試段階から“感情の切替”を練習しておく。
8. 推し教材・音源の使い分け
8-1. 公式問題集の型化
公式問題集の言い回しに慣れるのが最短。ノートは「場面→言い換え→設問タイプ→根拠文」の4列で整理し、先読みメモへ還流。図表は「表題・軸・凡例・例外印」の4点チェックをテンプレ化。
8-2. パート別解説書/精選模試の活用
パート別解説書で先読み・意図問題の考え方を理解し、精選模試で難度耐性を作る。週次で「模試1セット=30問」を定点観測に。
8-3. 無料音源(ニュース・Podcast)
ニュース系は数字・固有名詞・CTAが多く、Part4の耳作りに相性◎。通学・通勤の隙間に1.25倍で流し、シャドーイングは1トピック30秒×3回を目安に。
まとめ
Part4は“設計を理解し、型で処理”すれば必ず伸びます。前提は「10トーク×3問=30問」「本文は音声のみ、設問は紙で見える」「後半で図表が出やすい」。対策は①先読みの型(疑問詞+名詞→差分語だけ拾う)を作る、②タイプ別の聞き方(広告/留守電/案内/図表)で耳を置く場所を固定、③演習ループ(通し→精読→ディクテ→シャドー→再演習)で処理を自動化。時間配分は「先読み7〜10秒」「2秒迷ったら損切り」「後戻りしない」。スコア帯別には、〜600は語彙と型の同時進行、700帯はテンプレ運用の高速化、800+は意図・図表の満点化を重視。教材はまず公式問題集、図表は束練で“見る順”を身体化。ノートには「正解の理由/誤答の理由/どの段でミスったか」を残し、翌日の先読み・聞き取りに反映。これを1日90分で回せば、1〜2週間でセットごとの安定感、3〜4週で「9/9が時々出る」状態に入ります。まずは本記事のテンプレを1セット使い切り、スコア表で“落ちている設問タイプ”から順に潰していきましょう。