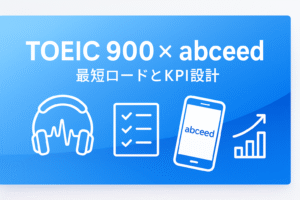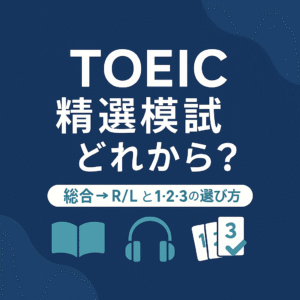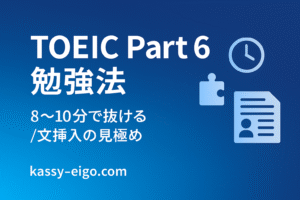TOEIC Part3(会話問題)は「先読みの型」「物語として聴く枠組み」「図表の変更点先取り」の3本柱で一気に伸ばせます。本記事では、試験中の動き方から日々の練習メニュー(30分/60分)まで、再現性の高い手順で解説します。
1. Part3の概要と“難所”の正体
1-1. 出題形式と分量(まずは39問の構造を知る)
Part3は会話13本×各3問=計39問。紙面にあるのは質問文と選択肢のみで、会話は音声のみ。職場・店舗・出張・イベント準備などが題材です。1セットは約1分弱の集中を要し、先読み→聴取→即マーク→次先読みのサイクルを13回繰り返す競技だと捉えましょう。まずは“物量”を前提に、時間・集中力の配分を設計することが出発点です。
1-2. つまずきやすい理由(情報量・話者数・図表)
失点原因は主に3つ。①情報量:設問が3本で問われ方が多様。②話者数:3人会話で役割と言い換えに翻弄されやすい。③図表:予約表やスケジュールなど“変更点”の把握が必要。対策は、設問パターンの型化、役割語の先読み、図表の概要→変更候補の順で“何を拾うか”を事前決定してから聴くことです。
2. スコアが伸びる「先読み」の型
2-1. ベストなタイミング(Directions/設問読み上げ中)
先読みはタイミングが命。流れは「(前セットをマーク)→次セットの質問3本を先読み→会話→即マーク」。図表がある場合は、先に種類・列名・単位・目立つ数字だけを確認して話題予測を立てます。Directions中に3問すべて読めなくても、1〜2問+図表の概観で十分。要は聴く直前に“拾う情報”が決まっている状態を作ることです。
2-2. 3問セットの読み方(5W1H→キーワード化→予測)
各問は5W1Hの骨格で捉え、頭に残すのはキーワード1〜3個。例:Q1(全体)=場面/テーマ、Q2(個別)=理由・原因、Q3(個別)=依頼・次の行動。選択肢は流し見しつつ、confirm=make sure, leave=drop off などの言い換えネットを張っておき、聴取中にひっかかる語を待ち受けます。
3. 会話を“物語”として聴く
3-1. 目的・課題・行動の三点取り
会話を目的(why)→課題(何が問題)→行動(どうする)の三点で要約すると、設問の大半に対応できます。冒頭で目的(予約変更・納期・案内など)を掴み、中盤で課題や変化点(delay, out of stock, reschedule)を特定、結末で行動(email, confirm, pick up)を把握。数字・日時・場所はメモ記号で圧縮し、骨(結論)を優先して拾いましょう。
3-2. 3人会話の聞き分け(役割と言い換え)
3人会話は役割語の先読み(manager/technician/client など)が効きます。冒頭1〜2往復で誰が何者かを確定し、以降は役割×目的で紐づけて記憶。内容は言い換えで出るため、we’re short-staffed→hire a temp staff のような因果を追い、迷ったら最後に決まった行動を優先して答えます。
4. 図表問題の攻略
4-1. 先に見るべき箇所(概要・変更点)
図表は全体像→変更候補の順で。まず種類(時刻表/料金表/予約表)、列名、単位、突出した数字を把握。次に変わりそうな軸(日付・時刻・価格・担当)に目星をつけ、聴取でそこが更新されるかだけを追います。全部を読むのではなく、“どこが動くか”に的を絞るのがコツ。
4-2. 典型的な引っかけと回避法
ありがちな罠は、(a)似た固有名詞(Mon/Mon.15)、(b)旧→新の切り替え、(c)“最初の案”と“確定案”の混在。回避策は、最新決定事項に下線、旧情報に斜線や×印をつけて視覚的に確定させること。数値は必ず単位とセットで確認します。
5. 要点メモとリテンション
5-1. 記号テンプレ(→, △, $, ETA など)
書きすぎは禁物。以下の最小記号セットで圧縮します:
→(次の行動)/△(課題)/✓(確定)/×(取消)/$(費用)/@(場所)/ETA(到着時刻)/Mo/Tu/W(曜日略)/12.5(12:30の簡略)。人名・役割は頭文字(M, T, C)で良いです。
5-2. メモ量の最適化(聞く>書くの優先)
原則は聞く8:書く2。メモは“後で選択肢と照合するためのフック”と割り切り、全文記録はしない。Q1は場面語、Q2は理由語、Q3は依頼語のキーだけ残し、聴取の集中を切らさない運用を徹底します。
6. 音声変化×理解の底上げ
6-1. 連結・弱形・同化の最短ドリル
正確に聞くには音声変化の体感が必須。教材1会話につき、(1)スクリプト確認(連結・弱形をマーキング)→(2)1文ずつゆっくりオーバーラップ→(3)ナチュラル速度でリピート、の3工程を回します。1日10〜15文で十分。
6-2. チャンクリーディングの導入
英語は意味の塊(チャンク)で処理します。スラッシュで区切り、目的→課題→行動の塊ごとに意味を即復唱。慣れたらスラッシュを外し、チャンクの感覚のまま通読→オーバーラップへ。
7. 30分/60分トレーニング
7-1. abceed/スタディサプリの使い方
30分版:
・5分:音声変化マーキング(1会話)
・10分:オーバーラップ→リピート(1会話)
・10分:先読み→本番速度で解答(1会話)
・5分:解説→メモ反省(過剰・不足の確認)
60分版は各工程を倍にして2会話×精緻で回します。予測スコアや弱点タグを活用し、3人会話/図表持ちを優先的に反復。
7-2. シャドーイング→ディクテーションの順序
まずシャドーイングでリズムと連結を身体化→詰まる箇所のみ部分ディクテーションで穴埋め。全文ディクテーションは時間対効果が落ちるためピンポイント運用に留めます。
8. レベル別ロードマップ(600/700/800)
600点帯:先読みテンプレの確立とQ1正答の死守。1日30分、3人会話と図表を毎日1本。
700点帯:Q2/Q3の理由・依頼特化で精度を上げる。言い換え対策を単語帳ではなく会話中の再現で。
800点帯:メモ量をさらに削って処理速度を上げる。設問の意図予測→根拠箇所1回聴取で即答のワンパスを磨く。
9. 当日の時間配分とマーク戦略
先読みは常に次セットに先投資。迷ったら“最後に決まった行動”を優先し、長考は禁物。塗りミス防止のため、各セット終了時に1秒だけ視線確認。塗れなかった番号には小さく点を付け、見落としゼロを徹底します。
まとめ
Part3の鍵は、先読みの型化、物語聴取(目的→課題→行動)、そして図表の変更点先取りです。練習では音声変化の体感→シャドーイング→部分ディクテーションで“聞ける耳”を育て、30分/60分メニューで毎日回す。試験では、先読みで拾う情報を決め、会話中は骨だけを掴んで即マーク→次先読みへ。これで迷いが消え、正答率と処理速度が同時に伸びます。今日からテンプレを1会話で良いので回し、1週間で“先読み→即答”の自動化を完成させましょう。

かっしー
TOEIC770点 → 900点を目指して勉強中✍️
2025年10月に英検準1級を受験予定です。
独学で積み上げた学習法や教材レビューを発信中。
「効率よく成果を出す英語学習」をテーマに、ブログとXで情報をシェアしています。